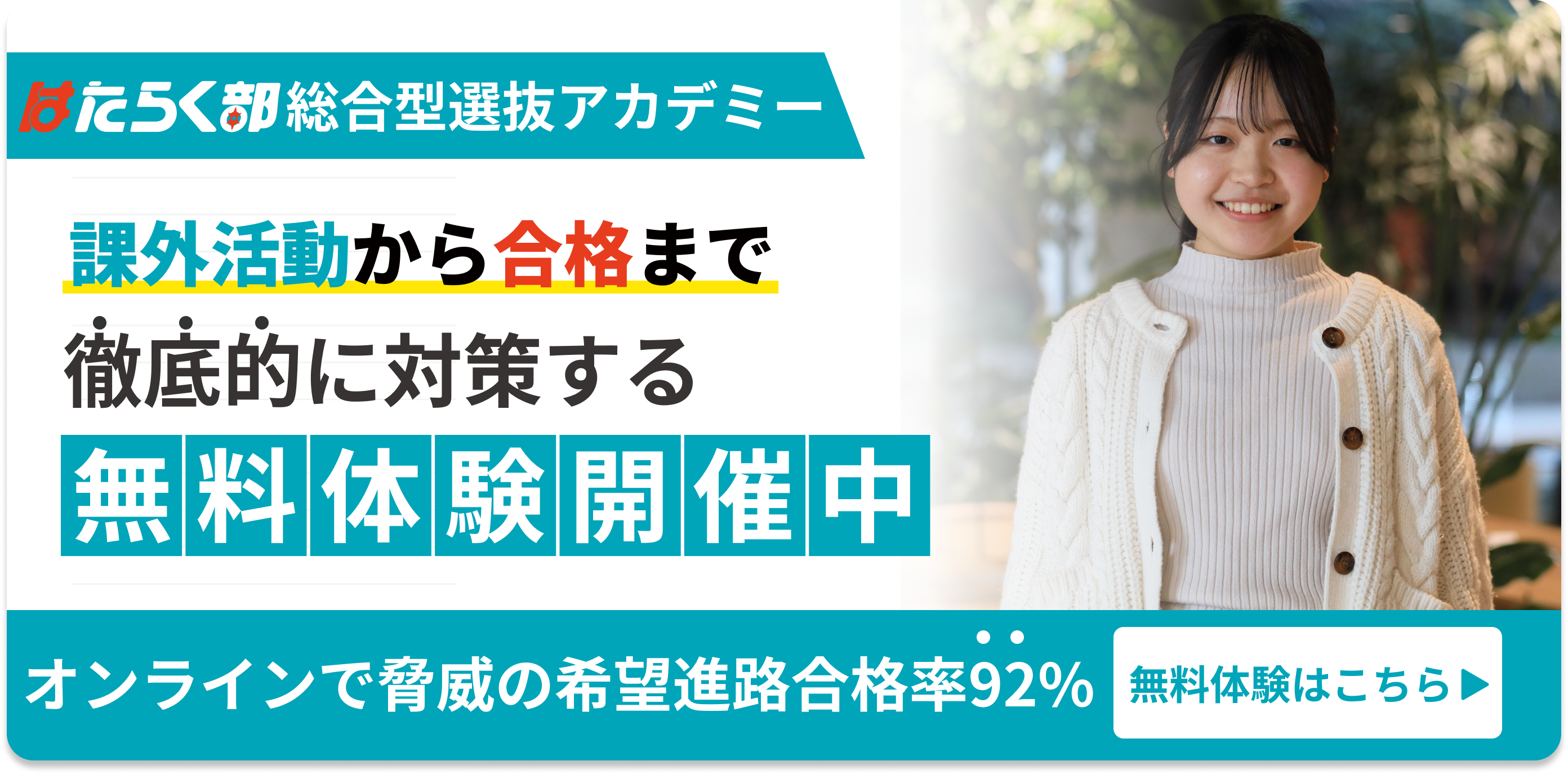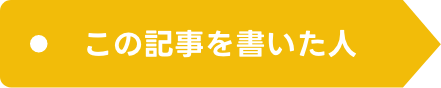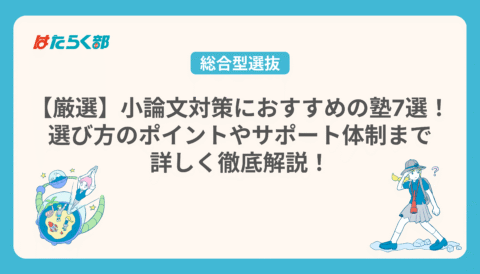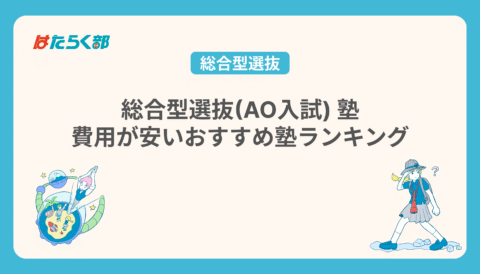ブログBlog
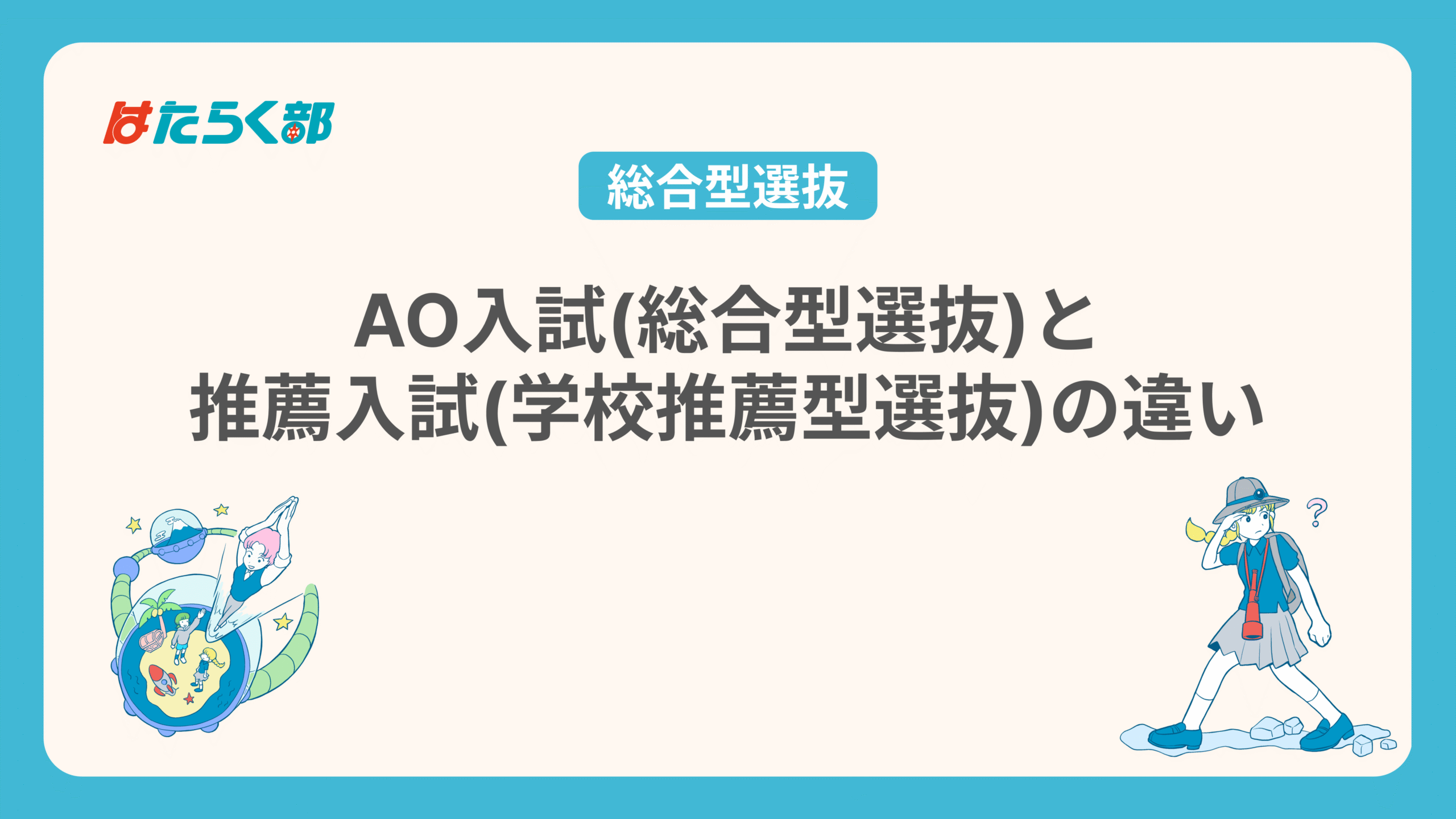
AO入試(総合型選抜)と推薦入試(学校推薦型)の違い

「志望校に合格できる可能性を広げたい」
という気持ちから、一般入試以外の受験方式に興味を持つ方も年々増えています。
この記事では、AO入試(総合型選抜)と推薦入試(学校推薦型)の違いを一目でわかるように表でわかりやすく比較し、それぞれの特徴やメリット・デメリット、向いている人の傾向まで詳しく解説します。さらに、2025年度の各大学の入試情報もまとめました。
この記事を読めば、あなたやお子さんに合った受験スタイルのイメージが具体的に描けるようになります。
AO入試(総合型選抜)と推薦入試(学校推薦型)とは
大学入試には学力で合否を判定する一般選抜だけではなく、人物評価や多面的な力を重視する入試方式があります。その代表が「AO入試(総合型選抜)」と「推薦入試(学校推薦型)」です。どちらも学力試験だけでなく、面接や書類などを通して受験生の個性や適性を見極めますが、出願条件や評価方法、求められる準備には大きな違いがあります。ここではまず、それぞれの入試の基本を整理しましょう。
AO入試(総合型選抜)とは
AO入試(総合型選抜)とは、大学側が求める学生を選抜する入試です。そのため、学生は「自分がその大学にふさわしい人物である」とアピールする必要があります。
総合型選抜では「何を学びたいのか?」「その学びをどのように活かすのか?」などが問われ、それらを志望理由書や面接、小論文、プレゼンテーションなどの多様な方法で審査されます。
推薦入試(学校推薦型)とは
推薦入試(学校推薦型)は高校の推薦を受けて出願する入試方式で、高校での評定平均や出席状況、活動実績などが重視されます。推薦入試(学校推薦型)には2種類あります。1つ目の「指定校推薦」は枠が限定され合格率が高く、2つ目の「公募推薦」は幅広い受験生が対象です。調査書の重要度が高く、合格後は辞退不可が多いため早期に進路が決まるのが特徴です。
AO入試(総合型選抜)と推薦入試(学校推薦型)の違い
| 項目 | AO入試(総合型選抜) | 推薦入試(学校推薦型) |
|---|---|---|
| 出願条件 |
AO入試(総合型選抜)
推薦不要 |
推薦入試(学校推薦型)
学校推薦必須 |
| 出願時期 |
AO入試(総合型選抜)
9月〜11月頃 |
推薦入試(学校推薦型)
11月以降 |
| 併願可否 |
AO入試(総合型選抜)
大学によって併願可 |
推薦入試(学校推薦型)
基本併願不可 |
| 主な試験内容 |
AO入試(総合型選抜)
書類・面接・小論文・プレゼンテーションなど |
推薦入試(学校推薦型)
書類・面接・小論文・学力試験ありの場合も |
| 評価の基準 |
AO入試(総合型選抜)
大学と受験生のマッチング |
推薦入試(学校推薦型)
成績(評定平均)、出席率、学校生活態度 |
| 選考方法 |
AO入試(総合型選抜)
多面的・総合評価 |
推薦入試(学校推薦型)
成績・人物評価を中心 |
| 合格後の進路変更 |
AO入試(総合型選抜)
大学によっては辞退可 |
推薦入試(学校推薦型)
基本辞退不可 |
| 向いている人の特徴 |
AO入試(総合型選抜)
自己PR力があり計画的に準備が出来る人 |
推薦入試(学校推薦型)
成績や出席率に自信があり早期合格したい人 |
| 向いていない人の特徴 |
AO入試(総合型選抜)
自己分析や準備が苦手、将来像が不明確な人 |
推薦入試(学校推薦型)
日頃の成績や出席率に不安がある人、進路未決定の人 |
出願条件
AO入試(総合型選抜)は学校からの推薦が不要で、幅広い受験生が挑戦できます。課外活動や特別な実績がなくても志望理由や適性をしっかり示せば受験可能です。ですが、大学によっては評定平均や出席日数などに関して指定がある場合もあるので注意しましょう。
一方、推薦入試(学校推薦型)は高校からの推薦が必要で、評定平均や出席日数、生活態度など明確な基準が設けられるのが一般的です。
出願時期
AO入試(総合型選抜)は9月〜11月頃と早期に募集が始まることが多く、7、8月が1番準備に追われます。そのため、夏休み中に志望理由書や活動報告を準備できる人に向いています。
推薦入試(学校推薦型)は11月以降に実施され、高校での定期テストや評定が確定したあとに出願する流れが一般的です。
併願可否
AO入試(総合型選抜)は大学や学部によって併願可能な場合が多く、複数校にチャレンジできます。
推薦入試(学校推薦型)は基本的に併願不可で、1校に絞って受験する必要があります。
主な試験内容
AO入試(総合型選抜)は、面接・小論文・プレゼン・活動報告書を通じて受験生を多面的に評価します。たとえば、ボランティア活動をしてきた人なら「その経験を大学での学びや将来の仕事にどうつなげるか」といった具体性が問われます。
推薦入試(学校推薦型)は書類審査と面接が中心です。必要に応じて学力試験を課す大学もありますが、基本は「日頃の学校生活の積み重ね(成績や態度)」が重視されます。
評価の基準
AO入試(総合型選抜)は、志望理由や学校外での活動実績、将来性を評価します。いかに志望大学と自分がマッチしているかが重要です。たとえば「アルバイトで培った接客スキルを観光学部で活かしたい」といった関連付けが強みになります。
推薦入試(学校推薦型)は、評定平均や出席率、授業態度を基準に評価します。つまり、定期テストで安定した点数を取れているか、遅刻や欠席が少ないかといった日常的な努力がカギです。
選考方法
AO入試(総合型選抜)は面接や小論文、提出資料を総合的に見て判断する多面的評価が特徴です。
推薦入試(学校推薦型)は成績・人物評価を中心とした学校生活重視の評価で、安定した実績を持つ受験生に有利です。
合格後の進路変更
AO入試(総合型選抜)は大学によって合格後の辞退が可能な場合があります。
推薦入試(学校推薦型)は基本的に辞退不可です。
「推薦を受けた=その大学に進学する」という前提で進められます。高校と大学の信頼関係に基づく方式なので、軽い気持ちで受けるのはNGです。
向いている人の特徴
AO入試(総合型選抜)は、自己表現が得意で、志望理由や将来の方向性が明確な人に向いています。学校外の活動で、大学4年間、さらには人生を通して学び続けたいと思えるものがある人は特に向いています。
また、計画的な準備が得意な人も挑戦しやすいです。
推薦入試(学校推薦型)は、評定平均や出席率に自信があり、早期に進路を確定したい人向けです。
推薦入試では、1大学につき高校から推薦を出せる人数が限られているため、推薦を希望する人数が多くなった際には成績や欠席数など総合的に評価し、選ばれます。そのため、現在高校での定期試験で上位を獲得しており、出席も公欠以外で欠席や遅刻をした事が無い学生が特に向いていると言えます。
向いていない人の特徴
AO入試(総合型選抜)は、志望理由や将来の方向性がまだ定まっていない人や、自己分析や計画的な準備が苦手な人には向いていません。
推薦入試(学校推薦型)は、評定平均や出席率に不安がある人や、進路を一つに絞らず幅広く受験したいと考えている人には適していません。
AO入試(総合型選抜)と推薦入試(学校推薦型)のメリット・デメリット
| 入試方式 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| AO入試(総合型選抜) |
メリット
|
デメリット
|
| 推薦入試(学校推薦型) |
メリット
|
デメリット
|
AO入試(総合型選抜)のメリット
出願条件が少なく幅広い受験生が挑戦できる
AO入試(総合型選抜)は、大学が掲げるアドミッションポリシーに合った人物であることが基本条件であり、評定平均値や模試の得点といった制約は比較的少ないのが特徴です。例えば、評定がそこまで高くなくても「地域活動での取り組み」や「自主的な研究テーマへの挑戦」などが評価され、出願できるケースがあります。そのため、学力試験だけでは自分の力を示しにくい受験生にも挑戦のチャンスが広がります。AO入試を考える際は、まず志望校のアドミッションポリシーを読み込み、自分の経験や強みと照らし合わせてみましょう。
個性や活動実績をアピールしやすい
AO入試は、高校内の成績や出席状況だけでは測りきれない「その人らしさ」が評価されやすい入試方式です。例えば、部活動でキャプテンを務めチームをまとめ上げた経験、地域のボランティアで得た学び、あるいは独学でプログラミングやデザインに挑戦した実績なども立派なアピールポイントになります。自分の将来像を明確に描き、その実現のために行動してきたプロセスが重視されるため、「学校外での挑戦」を強みにできる学生に特に向いていると言えます。
併願可能な大学も多く柔軟性がある
AO入試は併願可能な大学が多く、受験生にとって進路の選択肢を広げやすいのもメリットです。例えば、第1志望校のAO入試に挑戦しながら、別の大学のAO入試や推薦入試に並行してエントリーすることもできます。こうした柔軟性があることで、「自分に最も合った大学」を見極める機会が増えます。特に、将来像と大学の教育方針が重なると確信できる大学であれば、積極的に併願を検討する価値があります。
AO入試(総合型選抜)のデメリット(注意点)
書類や面接など準備に時間と労力が必要
AO入試(総合型選抜)では、いかに志望大学に受験生自身がマッチしているかをこれまでの活動実績などの根拠をもって証明する事が合格に繋がります。
そのため、出願までに自身の目標に沿った活動実績を着実に積む必要があります。
実績は一朝一夕で作れるものではないため、出願時期に合わせて計画的に早期からエンジン全開で意欲的に行動を起こす必要があります。
大学ごとに選考基準が異なり対策が難しい
AO入試(総合型選抜)は、大学ごとに評価基準や試験内容が大きく異なります。例えば、ある大学は小論文で社会課題に対する考えを問うのに対し、別の大学は面接で将来のキャリアビジョンを詳しく聞く場合もあります。また、プレゼンテーションやグループディスカッションを課す大学もあり、一律の対策では対応できません。そのため、志望校の入試要項を確認し、大学ごとに必要な準備を見極めることが重要です。
学力面で不安を抱えることもある
AO入試は学力試験を重視しない場合が多いため、入学後に授業についていけるかどうか不安を抱える学生もいます。例えば、理系学部では高校時代に数学や理科の基礎が不十分だと、大学での専門科目に苦労することがあります。文系学部でも統計学やデータ分析など数的処理を必要とする授業があり、基礎学力が不足していると大きな負担になります。合格をゴールとせず、入学後の学びを見据えて早めに基礎固めをしておくことが大切です。
推薦入試(学校推薦型)のメリット
高校での努力や実績が評価されやすい
推薦入試(学校推薦型)は、高校生活で積み上げてきた成績や出席状況、部活動・生徒会活動などが大きく評価される入試方式です。例えば、定期テストで常に上位の成績を収めてきた生徒や、無遅刻・無欠席を続けてきた生徒は、その努力がそのまま「信頼できる人物」として大学に伝わります。一般入試のように1日の試験結果に左右されにくいため、「これまでの積み重ね」をアピールできるのが大きな強みです。
合格率が比較的高く早期に進路が決まる
推薦入試は、学校から推薦を受けられる時点で一定の学力や生活態度が担保されているため、合格率が高い傾向にあります。また、一般入試よりも早い時期に合否が決まるため、高校3年生の秋頃には進路が確定するケースもあります。例えば、11月に合格が決まれば、その後は大学入学に向けた準備や、資格取得・趣味・アルバイトなどに時間を充てられるのも魅力です。
推薦枠で受験競争を回避できる
推薦入試では「高校からの推薦枠」があるため、一般入試のように数万人規模の受験生と競い合う必要がありません。例えば、同じ大学に推薦枠3名が割り当てられていれば、その高校内で推薦が得られれば受験のスタートラインに立つことができます。大規模な受験競争を避けたい人にとっては安心材料になります。
推薦入試(学校推薦型)のデメリット(注意点)
基本的に併願不可で柔軟性がない
推薦入試は「専願」が原則で、合格した場合は必ずその大学に進学しなければなりません。つまり、他の大学との併願ができず、進路の選択肢を狭めてしまう可能性があります。例えば、「推薦で合格したけれど、その後に別の学部に興味が湧いた」という場合でも、進路を変更することはできません。
推薦枠がない大学・学部では利用不可
すべての大学・学部に推薦枠があるわけではありません。人気の学部や私立大学の一部では推薦枠自体が設けられていないこともあります。例えば、「法学部は推薦枠があるが、国際学部には推薦枠がない」といったケースもあり、志望分野によってはそもそも推薦入試を利用できない場合もあります。そのため、事前に高校と大学の情報をよく確認しておくことが重要です。
合格後は辞退できず進路変更が難しい
推薦入試は「合格したら必ず入学する」というルールがあるため、合格後の辞退は基本的に認められません。もし辞退した場合、高校全体の信用に関わり、翌年度以降に推薦枠が減らされる可能性もあります。実際に、「合格後に別の学問に興味を持ったが、辞退できずにそのまま進学した」という学生も少なくありません。この点からも、推薦入試を受ける際は「その大学・学部で本当に学びたいか」を事前にしっかり考える必要があります。
推薦入試(学校推薦型)は、日頃の努力や成績を評価してもらいやすく、早期に進路を決定できる安心感がある反面、併願不可や進路変更の難しさというリスクも伴います。
どちらの入試方式で受験するか迷っている方へ
ここまでAO入試(総合型選抜)と推薦入試(学校推薦型)の違いについて解説してきましたが、自分一人で大学受験に関する決断を行う事は不安が伴うと思います。
また、受験方式の違いは理解したが、自分の進むべき方向が明確に定まっておらず入試方式の決断に踏み込めない人も少なくないと思います。
はたらく部アカデミーでは、総合型選抜や推薦入試で大学受験を目指す高校生向けに、自己分析・志望理由書の書き方・面接指導といったスキル面での対策はもちろんのこと、大学受験での進路相談だけでなく人生を通した受験生自身のキャリアを経験豊富な大人が一緒に考えてくれます。
私自身も自分の進むべき道が何もわからず大学受験をするかすらイメージがついていない状態でしたが、はたらく部アカデミーに入りたくさんの大人の方と話し、自分自身と向きったことで総合型選抜方式を選択し自分が納得できる形で大学受験を終える事が出来ました。
もしあなたが今大学受験、さらにはその先に進むべき道が分からず不安を抱えているのであれば自分の強みやキャリアを一緒に考えてくれる大人と出会える「はたらく部アカデミー」で真剣に自分と向き合ってみませんか?
🏆合格率92%!見れば納得、合格の秘訣はこちら!👇👇👇
総合型選抜(AO入試)専門塾で対策するならはたらく部アカデミー

足立陽菜
目標が無くなんとなく過ごした高校三年間。それでもはたらく部総合型選抜コースに出会い、真剣に自分の過去・未来に向き合った結果多くの気づきがありました。今は自身のパワーアップのためにはたらく部でのインターン活動のほかに大学での活動にも積極的に取り組んでいる真っ最中!